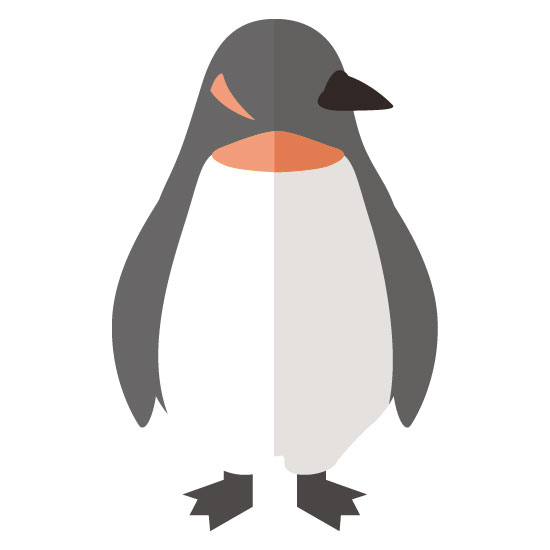この記事のお悩み
- うちは新卒を取らないからな…
- 中途採用は無いし常に人手不足で大変…
- 仕事のしわ寄せを解消したい!
と、このような悩みを解決できる記事です。
ここでお伝えする「人手不足による仕事のしわ寄せから逃れる方法」を読むと、仕事が楽になり、今あなたが抱えているストレスもグッと軽減されます。
少子高齢化や離職者の増加の影響で、人手不足による問題を抱えているのはあなただけではありません。
多くの人、企業が抱える重大な悩みです。
まずは「人手不足で起こりうる問題点」を挙げ、「しわ寄せが企業に及ぼす影響」から、「具体的な解決策」をお伝えしていきます。
本記事のリンクには広告がふくまれています。
人手不足で起こりうる問題点
では始めに、人手不足でしわ寄せが来た時に起こりうる問題点から。
ここで述べることは、人手不足と感じるあなたの会社で実際に起きている問題がきっと含まれていると思います。
なぜなら実際に私が経験したことや、ニュースで取り上げられたことをお伝えするからです。
それぞれの問題はとても重要で、人手不足を解消するには理解が必要です。
社内で起きている問題点を抽出し、適した対策を練っていきましょう。
人手不足で起こりうる問題点
- オーバーワーク
- 業務の兼任
- 休みが取れない、取りづらい
- 長時間労働
- 管理職が過酷な状況に追いやられる
- 組織の士気の低下
- 離職者の増加による状況悪化
オーバーワーク
人手不足になるとオーバーワークになる可能性が高くなります。
なぜなら単純に、そのポジションの仕事を請け負うことになるからです。
例えば貿易会社に勤めていて営業職に就いている場合、人手不足により営業事務がいないとしたら、書類作成や伝票発行まで行うことになります。
貿易に関わる手数料、仕入れ・支出などの細かい計算が必要なので、片手間でやるべき職務ではありません。
また、スキルが不十分で不慣れなことから時間がかかり、自ずと残業を強いられます。
別の社員が休んだり、間接的な人手不足の影響を受けた場合も、仕事の負担やトラブルに直面します。
オーバーワークで起こりうること
- 業務過多
- 残業、休日出勤
- 知識・経験不足
- 給与問題(割が合わない)
業務過多・兼任
小さな会社であれば、人手不足になるとより業務過多になり、仕事を兼任する機会が増えます。
1つの職務を全うし続けるより、知識、スキル、経験を得られるという面で見ると、兼任自体は良いことです。
しかし、コンビニやレストランなどの飲食店、小売業での人手不足は致命的です。
人手が足りなければ店を閉めざるを得ないのですが、少ない従業員で店を回すとなると、まともな休日を得られなくなります。
そして他の仕事をしたくても、時間や気持ちに余裕が無くなるのです。
医療業界では、医師・看護師・薬剤師の中で「タスクシェア」「タスクシフト」を推進することになりました。
2040年には業界内で96万人が不足すると推計されており、
- 医師の業務過多の軽減
- 医療従事者の質の向上
- 業務の効率化・循環
などの改善、人手確保に向けた動きを取っています。
私の身近なところでは、所属する部署の仕事を軸に、人手が足りていない別の部署をサポートする形が見受けられます。
ですが、仕事を兼任しても給与が変わらず、仕事は増え残業が続くことで、過労で心身を病んでしまう人も少なくありません。
休みが取れない、取りづらい
- シフトの希望を聞いてもらえず休めない…
- 有給の申請が通らない…
- 休暇の取りづらい雰囲気がある…
このような理由により、なかなか休みがとれないといった経験は無いでしょうか?
日本では年に10日以上の有給休暇を取得している場合、5日消化する義務があります。
しかし企業による有給に対する意識の違いから、有給を取りづらい職場環境が存在していいて、「仕事の負担が大きい」とか、「過労で身体の調子が悪い」「休日は寝て終わり」などと、自由に有給を使えない職場で働く人の悩みは深刻です。
私も休日出勤を繰り返し月曜の朝はほんと体がキツくて、常に頭がボーッとした状態で仕事をしていました。
十分に休めない状況は痛いほど分かります。
長時間労働を強いられる
人手不足は長時間労働を誘発します。
前述の通り、個人に対する業務過多、仕事の兼任を理由に、時間を消費する機会が増すからです。
するとストレスを抱え、慢性的な睡眠不足や食欲不振になり、益々仕事に悪い影響を及ぼします。
また、残業時間が80時間以上になると「過労死ライン」とも言われます。
心身の健康を損ねたり過労死につながる可能性があるので、長時間労働は命に関わるといっても過言ではありません。
中間管理職が過酷な状況に追いやられる
人手不足により、中間管理職の1人あたりの業務負担が重くなります。
本来、部下や後輩がする仕事を請け負うことになり、実務に専念できず、余計な仕事が増えてしまうからです。
板挟みになる環境が軽減されても、上司から一方的な要望を受ける形になり、逃げ場が無くなります。
また小さな組織ではそもそも業務の兼任が当たり前なので、課長、部長といった役職の立場にも飛び火するでしょう。
何気なく人に頼っていた仕事が多ければ多いほど、人手不足によるしわ寄せは肥大化します。
組織の士気が低下する
人手不足になると目の前にある業務をこなすことで精一杯になってしまい、楽しさや、やりがいを感じて仕事ができなくなります。
そんな毎日では、チャレンジする意欲や行動、変化への気力も生まれず、モチベーションの低下を引き起こしてしまいます。
意識や感覚に個人差はあるものの、組織全体の士気は下がる一方です。
また、フレックスやテレワークが普及した今、社員同士が顔を合わせないのが当たり前となり、会社の存在意義に疑問が問われています。
どの企業もこの問題に直面し、働き方を試行錯誤する日々が続いていますが、少なくとも業績が低下し、成長が停滞している企業が増えているのは間違いありません。
離職者の増加による状況悪化
そもそも人手不足は、高齢者の増加と少子化による労働人口の減少が原因です。
日本の場合、1980年頃までは出生2.0(人)以上だったのが、2021年では1.3(人)、2022年はそれを下回る1.2(人)と見込まれていて、労働の源となる若者がいません。
また、25歳〜34歳以外の労働参加者(15歳〜24歳、25歳以上)が全て減少していて、労働供給のバランスが崩れています。
企業は給与、労働条件の見直しを図り、人手不足を解消しようとしています。
しかし、転職が一般的になり、雇用条件の良い企業が増えると、企業間の雇用条件の競争が生まれ、雇用を確保することが難しくなるといった悪循環が起こります。
残念ながら人手不足を雇用だけで解消するのはとても難しい状況です。
人手不足によるしわ寄せが企業に及ぼす影響
近年、日本をはじめとする世界各国において、人手不足に悩む企業が増加しています。
企業が必要とする人材の供給が追いつかず、採用難が深刻な問題となっています。
そして人手不足により抱える課題、問題点の一つがしわ寄せです。
この現象は、企業が必要とする人材が不足しているため、残業や休日出勤が増え、業務が遅れることで発生します。
結果として次のような問題を引き起こし、企業に深刻な影響を及ぼすのです。
しわ寄せが企業に及ぼす影響
- 生産性の低下
- 品質の低下
- 遅延、配送の問題
- 売上の低下
- 顧客サービスの低下
- 人件費の上昇
- 従業員のモラルの低下
生産性の低下
人手不足による生産性の低下は、企業にとって深刻な問題となります。
人手不足によって、従業員が抱える業務量が増え、作業の効率や精度が低下してしまいます。
また、これが原因で従業員の疲労やストレスによる生産性の低下も併発します。
これにより生産性は低下し、企業の収益や競争力に大きな影響を与えます。
品質の低下
また、まともに業務処理が行えないと、品質の低下に繋がります。
製造業においては、人材不足による製品の不良や欠陥が発生した場合、顧客からのクレーム・返品などの問題を処理する形になります。
従来の業務に加え、クレームや返品処理に追われていては、より一層仕事が回らなくなります。
そして、このことにより企業の評判が低下し、信頼を失う可能性もあるのです。
遅延、配送の問題
遅延、配送の問題も、人手不足による企業における最も顕著な問題の1つです。
特に、製造業や物流サービス業では、製品の製造や物流のスケジュールに依存しているため、遅延や配送の問題が起こると、企業にとって大きな被害が生じます。
製品の生産ライン、物流センターで働く従業員が足りないと、製品や商品の仕分け、運搬作業が遅れ、配達のスケジュールに支障をきたしてしまいます。
そのため、労働時間やシフトの見直し、業務の自動化や外部のサプライヤーとの協力など、施策を検討する必要があります。
売上の低下
人手不足になると、製品やサービスの提供が追いつかず、顧客ニーズに対応できなくなります。
例えば店舗、レストランの場合、人手不足が原因で店内の清掃や調理、サービスの提供に支障が出ます。
結果として、顧客は長い待ち時間や不十分なサービスに不満を抱き、店舗への来店回数や支出額の減少に繋がるのです。
顧客満足度は、一度下がってしまうとなかなか元に戻せません。
取り戻すためには、効率的な業務プロセスの確立と施策が必要になります。
顧客サービスの低下
人手不足の状態でトラブルが続くと、ひとつひとつのサポートが手薄になります。
従業員の疲労やストレスによって、対応の品質や速度が低下し、クレームや悪い評判と、企業の信頼性に影響を与えます。
顧客サービスの低下を解決するためには、従業員の負荷を軽減するほかありません。
顧客からの問い合わせを効率的に処理するために、FAQやチャットボットなどの自動応答システムを導入するなど、適切なツールやシステムの導入が必要です。
人件費の上昇
人手不足が深刻化すると、企業は従業員を確保するために、人件費の上昇に直面します。
労働市場での需要が高まることで、従業員の賃金や福利厚生の要求が増え、企業はこれらの要求に応えるために必死です。
特に、需要の高い業界や地域では、従業員を確保するために、
- 賃金の引き上げ
- ボーナスの支払い
- 労働時間の縮小
- 働き方の多様性
と、様々な手当が必要となります。
これにより、企業の人件費は増加し、利益率が低下するのは間違いありません。
従業員のモラルの低下
人手不足による従業員の過剰な負荷やストレスは、従業員のモラルを低下させる可能性があります。
働く環境が悪化し、働きがいを感じられなくなると、モチベーションや生産性が低下し、企業の業績に悪い影響を与えます。
また、残業や休日出勤が増え、休日を失うかもしれません。
この状況では、従業員がストレスを感じ、過労やうつ病などの健康問題を引き起こす原因にもなります。
そして従業員のモラル低下は、企業の離職率の増加にも繋がります。
従業員が辞め、企業は貴重な財産を失う上に、採用や人材育成のコストを排出してしまうのです。
しわ寄せが企業に及ぼす影響
- 生産性の低下
- 品質の低下
- 遅延、配送の問題
- 売上の低下
- 顧客サービスの低下
- 人件費の上昇
- 従業員のモラルの低下
人手不足によるしわ寄せの解決策
人手不足になると、これまで述べた問題点から「仕事のしわ寄せ」を受けることになります。
もしもそのしわ寄せを受け続けたらきっと苦しみます。辛くなります。悲しくもなります。
「人手が足りない…」たったそれだけの理由で、あなた1人がしんどい思いをする必要はありません。
人手不足によるしわ寄せの解決策を、省力化と省人化の視点でお伝えしていきます。
人手不足によるしわ寄せの解決策
- キャパを把握し無理をしない
- 業務・作業に疑問を持つ
- 強い決断意識を持つ
- 中途採用を積極的に行う
- アウトソーシングの投入
- 労働条件の改善(人が辞めない会社づくり)
- 人材育成の体制づくり
- 女性・シニア・障害者人材の積極活用
- ITによる業務の省力化
- 外部契約として働く
- 会社を辞める
キャパを把握し無理をしない
人手不足で仕事が増えると、これまでの何倍もの時間と労力をかけることになります。
しかし力量の範囲は人によって異なります。何でもこなせる人もいれば、すぐにテンパってしまう人もいます。
それはみんなが同じスペックを持っている訳ではないからです。
そして無理をし続けると、身体に不調を感じ突如ダウンします。
ギリギリの状態を維持してはいけません。越えてはいけない一線の瀬戸際にずっといるのは危険です。
だから自分のキャパを把握して、「これ以上はヤバい」と気付いたら引き下がる。避けたり抑えたり、コントロールすることです。
業務・作業に疑問を持つ
今、しわ寄せで行っている業務や作業に疑問を持ってください。
なぜかと言うと、実はそれらは、そもそも必要性がないかもしれないからです。
例えばペーパーレスを推奨し始めた頃、「紙も印鑑も無くすべきではない」と文句を言う人がたくさんいました。
しかし今となっては紙よりデータファイルの方が利便性が良く、誰が押したか分からない捺印より、ファイルにある記録データの方が正確なのは明らかです。
例えその時はほんの小さなことだと思っても、積み重なると大きな負担になります。
ひとつひとつの業務・作業に疑問を持てば、これまで気付かなかった発見や事実を知ることができます。
強い決断意識を持つ
器用貧乏な人ほどしわ寄せが来ます。
なぜなら断ることも頼むこともしないため、仕事は増える一方だからです。
「やる」と「やれる」は違います。「やる」は自発的ですが「やれる」は受動的です。
だから「やれること」は止めて「やること」だけと決意するのです。
立場上、断れないケースもあります。
ただ、あなた以外の人ができるのであれば、誰かに頼める「やれること」なので、『〇〇はやらない』と決断しましょう。
中途採用を積極的に行う
少子高齢化が進み、新卒採用で若い人材を集めるのが難しくなってきています。
そこで重要なのは、社会経験が豊富な人の「中途採用」を積極的に導入する方法です。
社会経験を積んだ人を雇うと、研修・教育に余計な時間とコストをかけずに済みます。
それにその人の持つ職能、スキルを活かせば即戦力になるのは間違いありません。
人手不足を解消するには、単に人を補充するだけではなく、その職種で活かせる能力を持つ人でなければいけません。
中途採用であれば能力の高い人が集まり、しわ寄せを素早く解消できる可能性が高まります。
アウトソーシングの投入
過度な業務で自社で回しきれない場合、必要な労働力を外部委託する方法があります。
かつてはExcelで表計算したり内職程度の簡単な仕事ばかりでしたが、個人や副業が増えたことにより、仕事の振り幅が大きく変わりました。
アウトソーシング例
- システムエンジニアなどの技術系商品開発
- 医療機器のコンサルティング
- SNSを使った商品、サービスの販促
専門職の場合、専門性や高度な知識を持ったプロの方が存在し、業務品質が高く、スピーディーに行ってくれます。
新たな雇用を生むより、確実に時間もコストもかかりません。
ただひとつ注意したいのは、アウトソーシングには「納期を守れない人が多い」というところ。
これを回避するには、1人に集約させずに、複数の人に仕事を振りリスクを分散させることです。
クラウド型アウトソーシングについては、『クラウドソーシング比較オススメ13サイト"』を参考にしてみてください。
労働条件の改善(人が辞めない会社づくり)
単純に、これ以上辞める人が増えないよう、賃金や処遇、労働環境の改善をすすめる方法です。
分かりきった内容かもしれませんが、
- 給与のアップ
- 成果型報酬
- 有給消化の義務化
- 残業手当
- ポジションを与える
といった方法を会社が取り入れ、提言していくことです。
あるいはリモートワークの導入や副業の容認など、社員に働きやすさ、やりがいを柔軟に提供し、退職率を下げます。
とは言え社員が決めることではないので、会社のトップに提案したり交渉が必要です。
人材育成の体制・環境作り
せっかく人を採用しても、働きがいや魅力を感じられる職場でなければ離職してしまいます。
働きやすいと感じてもらうには、人を育てる体制や環境作りが大事です。
マニュアル、指導する人、研修期間など、人材育成のパッケージを用意し、「この会社は大丈夫。」と安心感を与える。
就労後、仕事に対する不安を解消させるために、しっかりと情報を共有し、定期的に面談を行ったり相談しやすい環境を作る。
入社する人が働きやすさ、働きがいを感じられる環境にするためには、職場の人間関係が肝となるでしょう。
「人間関係の構築が苦手…」という人は、『人間関係が上手い人に共通する特徴。彼等が絶対にやらない"あること"とは?』を読んでみてくださいね。
女性・シニア・障害者人材の積極活用
人材を募集する際、女性、シニア、障害者といったターゲットにも目を向けてみましょう。
なぜなら彼らは仕事に対する意欲が高く、離職する可能性が低いからです。
- 結婚や育児を理由に仕事を辞めざるを得なかった女性。
- 定年を迎えた後も現役として活躍できるシニア層。
- 過去に仕事、職場環境に悩まされ障害を乗り越えた人。
このような人達に対し、これまでの労働形態にとらわれず、時短やリモート、ダブルワークの容認など、その人の状況に合わせ柔軟な働き方を推奨すること。
例えば主婦の場合、子どもの都合で休まざるを得なくなるし、私の父もそうでしたが、シニア層はPCなどの機械操作が苦手であったりします。
そのため、その人達への理解と協力無くして働くことはできません。
また、うつ病や総合失調症、障害を持った人などを支援する転職サイトがあります。
取材に伺ったゼネラルパートナーズという会社では、生徒さんが社会復帰のカリキュラムを受けていました。
社会復帰まで半年から1年ほど期間を設け、就職が決まった後もサポートし続けているそうです。
働きたい人を支援する企業・団体は多く存在するのですから、受け入れる企業も増えるべきだと思います。
ゼネラルパートナーズ支援型転職サイト
・atGPジョブトレ 統合失調症コース
統合失調症専門の就労移行支援
https://www.atgp.jp/training/course/togo/
・atGP 障害者転職サポート
障害者転職サポート実績業界No.1
https://www.atgp.jp/
ITによる業務の省力化
人手が足りず仕事が回らない場合、IoT、AIを活かし、業務効率や生産性をあげるのも1つの手です。
例えば「RPA」を使えば、伝票入力などの事務処理から、データ分析、ECサイト業務を自動化できます。
RPAは人が感じる面倒な単純作業をしてくれるロボット。
月10万〜程度で済むため人を雇うよりコストがかかりませんし、ロボットなので辞めるリスクもありません。
辞めた人のポジションを穴埋めするのは、何も人でなくても良い。
人にしかできない仕事と、ロボットでできる仕事の住み分けが、今後の働き方に大きく影響します。
外部契約として働く
会社にいると仕事のしわ寄せは増える一方です。
職場にいる時間、出勤日数を減らせば、不要な業務から逃れられるので、雇用形態を変えれば解決します。
つまり、個人事業主として、または会社を作って外部契約として働くことです。
同等の給与を貰えるかは個人の能力次第ではありますが、拘束時間が解消されるのは確かで、仕事の規制を緩和することもできます。
何か自分でやりたいことがあって、会社がそれを妨げているのなら、契約社員として働くことはひとつの選択肢です。
会社を辞める
もしも仕事がキツくなり耐えられない状況が続くようなら、会社を辞めるしかありません。
「年齢的に辞めるのが怖い…」
「不景気だから再就職できるか不安…」
といった悩みはあるかもしれません。
しかし会社とは、誰かが抜けても代わりはいくらでもいて、裏を返せば、どこでも働き口はあるということを意味します。
仕事を辞めるのが怖いのなら、何か副業をして収入源を増やしてからでもいいです。
実際に私も会社に所属しながら別の仕事をしていましたし、そもそも副業なんてずっと昔からあることで、例え会社がNGだとしても、辞める前提ならこっそり進めればいいと思います。
これからも仕事が苦痛で、いつまでも耐え続けている景色を想像してみてください。
会社に居続けるという選択肢が薄れていくはずです。
何よりしわ寄せから逃れることです
ここでお伝えした「人手不足によるしわ寄せの解決策」を実行すれば、きっとしわ寄せは軽減します。
その中でも以下の3つは自分で実行できることです。
なので、まずはあなたの力でしわ寄せを回避する努力をしてみてくださいね。
人手不足によるしわ寄せの解決策
- キャパを把握し無理をしない
- 業務・作業に疑問を持つ
- 強い決断意識を持つ