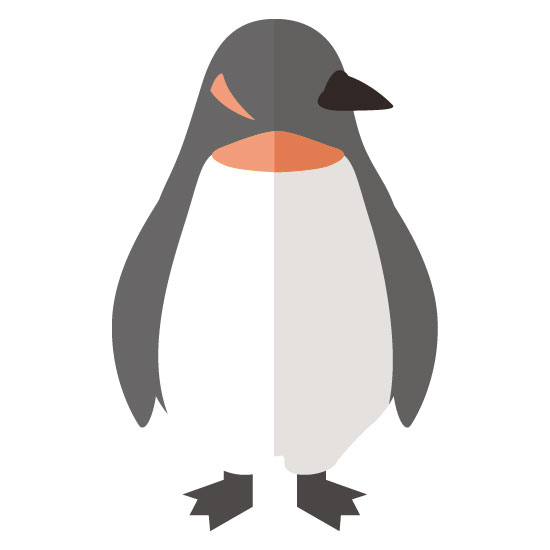こんな人におすすめの記事
- 仕事の責任が重くて辛い。
- 周りからの期待に応えられるか不安。
- 自分にできる自信がない。
あなたは今こんなことに悩まされていませんか?
ここでは「仕事の責任が重いと感じて悩む人」へ、その責任を軽くするコツや、苦しみから抜け出す方法をまとめています。
本記事を最後まで読み終えると、今あなたが抱えている仕事の責任は必ず軽くなります。
結果として、仕事に対してストレスを感じなくなりますよ。
本記事のリンクには広告がふくまれています。
責任を重く感じる最大の原因は?
結論から述べると、責任を重く感じるのは自分にプレッシャーを与えているからです。
そのプレッシャーが責任を更に重くし、自分を追い込んでいるところに原因があります。
しかし、今この記事を読んでいるあなたは、その責任を大きく受け止め、何とかしようと努力しているはずです。
つまり、逃げるという選択肢はあるのに、逃げずに解決しようとしている強者。
だからまずは、そんな勇敢な自分を褒めてあげましょう。
「やってやる!」という強い気持ちを持つ、自分の背中を押してあげてください。
責任の重い仕事をすべき理由とは?
責任の重い仕事を与えられているのは、「すごく良いこと」であると捉えてください。
なぜかと言うと、あなたへの期待と信頼が無ければ、責任のある仕事は与えられないからです。
私自身も若手の頃、責任のある仕事を怖く感じたことがあります。
その時、まずは向き合って、やってみることが大切だと思いました。
実際に責任のある仕事をしてみたところ、次のような経験を得られました。
- 納期に間に合わせた時に感謝をされた。
- 責任が信用に繋がり仕事が増えた。
- 仕事を効率的に回せるようになった。
- 自分にしかできない仕事が増えた。(やらなくて良い仕事も見つかった)
逃げるのは簡単だし、いつでもできます。
しかし、一度逃げてしまうと癖になるし、簡単な仕事しかできなくなってしまいます。
だから責任の重い仕事を引き受けたら、自分は会社にとって必要とされているのだと、自信を持つべきです。
責任が重いと感じてしまう理由
ではまずは、「この仕事、荷が重い…」と感じてしまう理由を噛み砕いて分析してみましょう。
ただ責任が重いと感じるより、なぜそう思っているのかを分析し理解することで、気持ちが楽になります。
悩みや不安は必ず元となる原因があるので、ここで述べることが自分に該当していないか?を確認してみてください。
責任が重いと感じてしまう理由
- 自分のキャパを越えている
- 未経験、未知の分野で自信がない
- トラブルやミスが起きないか不安になる
- 周りの期待に応える、結果を出せる気がしない
自分のキャパを越えている
1つ目は、自分のキャパを越えているからです。
新たに仕事を与えられると、今抱えている仕事に負荷がかかるので、単純にキャパオーバーしてしまうことに不安を感じます。
ましてやその業務内容の難易度が高ければ高いほど、時間やノルマが加わり、余計に仕事を引き受けたくなくなるのです。
既にキャパを越えている場合は、「なぜ自分に仕事をさせるのか」とイライラが募り、会社や上司に対する不満が生まれます。
責任の重い仕事は、もはやイジメだと感じてしまうのです。
未経験、未知の分野で自信がない
2つ目は、未経験、未知の分野で自信がないからです。
責任の重い仕事は、基本的にこれまで経験したことのない、未知の分野だったりします。
例えば営業職の人が、
- 今後販売する商品開発のために本格的なマーケティングを行う
- 予算設定や生産性の改善など販売戦略を練る
と、これまでものを売るだけだった人が、
組織全体を見たり、業務の構想を考える立場
になると、仕事の中身がガラッと変わり、大きな不安を抱えてしまいます。
仕事が増える分、既存の業務を減らしたり改善するなど、考えることがいっぱいで焦りも生じます。
トラブルやミスが起きないか不安になる
3つ目は、トラブルやミスが起きないか不安になるためです。
責任の重い仕事は、未経験のことばかりです。
「何も起きないように…」
「漏れがないように…」
と、神経を尖らせてしまうので、気持ちに余裕がなく、ひどくストレスを感じてしまいます。
残念ながらトラブルやミスは付き物で、必ずと言っていいほど何か起きます。
そんな時、「あぁ、やっぱりやらなきゃ良かった」と後悔するのです。
周りの期待に応える、結果を出せる気がしない
4つ目は、周りの期待に応えたり、結果を出せる気がしないからです。
責任の重い仕事には、「こうなって欲しい」という期待と結果が伴うものです。
しかしそれが負担となり、本来の自分らしさを失い、間違った方向に進んでしまう可能性があります。
私はできもしないことや余計な行動を取り、結果を出せず、期待に応えられなかった経験があります。
使い慣れていないソフトを使い、デザインに凝った資料作りをし、無駄な時間と労力をかけ、寝不足と疲労だけが残りました。
たった1度の失敗が自信を失わせることもあれば、そもそもできる自信がない場合もあります。
- 周囲からの期待が怖い…
- 結果に辿り着けるとは思えない…
そんな自分を想像するのです。
仕事に責任感を持つメリット
仕事に対する責任感を持つと、キャリアアップや信頼関係の確立、達成感や満足度など様々なメリットをもたらします。
ここではどのようなメリットがあるか詳しく解説していきます。
仕事に責任感を持つと得られるメリット
- 信頼性が高まる
- カリキュラムが向上する
- キャリアアップのチャンスを得られる
- チームのモチベーションが上がる
- 品質が向上する
- 緊急時の対応力が身につく
- 収益アップに繋がる
- リーダーシップの育成
- 将来への投資
信頼性が高まる
仕事に対して責任感を持つことにより、必然的に周りから信頼性が高まります。
極端な話、仕事を途中で投げ出すような適当な人に、「この人に仕事を任せたい!」と思う人は1人もいないはずです。
責任感を持って、次のことを繰り返すことで、周囲から信頼され関係性が深まります。
- 「約束を果たす」
- 「クオリティを維持する」
- 「納期を守る」
- 「素早く対応する」
カリキュラムが向上する
責任を持って仕事をこなすと、自分自身のスキルや知識が向上します。
例えば、仕事で出くわす問題を解決するには、新たなスキルやテクニックを学びますよね。
それに様々な仕事に携わることで、関連する知識や専門的な知識が身につきます。
このように責任を持って仕事をこなすことで、自身のスキルや知識が向上し、キャリアアップに繋がるのです。
キャリアアップのチャンスを得られる
責任を持って仕事をこなすと、上司や同僚から評価され、キャリアアップのチャンスが生まれます。
なぜなら仕事に対する姿勢は評価に直結するからです。
責任を持つと意識が変わります。そして次のような行動をおこします。
- 仕事の成果に対して自己評価を行う。
- 改善すべき点を見つける。
- スキルや能力を向上させる。
- 新たなチャレンジをする。
これらの行動から上司や同僚からの信頼が高まり、キャリアアップする可能性が上がります。
チームのモチベーションが上がる
責任を持って仕事をこなすことは、チームのモチベーションに影響します。
あなたがその姿勢を見せれば、チームの士気が高まり、結束を促すことになります。
その結果、一人ひとりが刺激を受け、仕事により熱中できるようになる可能性が高いのです。
やる気やモチベーションが上がれば、仕事の質、処理できる量も大きく影響するに違いありません。
品質が向上する
仕事に真摯に向き合うと、品質の向上にも繋がります。
ひたむきに仕事に取り組むことで、当然ながらクオリティに磨きがかかり信用にも繋がります。
お客様のニーズやウォンツを満たすために、プロセスを洗練させることができれば、最高のサービスを提供できます。
品質が向上するということは、お客様の満足度も上がることに繋がり、それが成果として表れるのです。
緊急時の対応力が身につく
対応力は、予想外のトラブルや問顟に対して柔軟に対応できる能力を意味します。
仕事では特に、予想外の事態が発生したときに求められます。
良い対応力を持っている人は責任感が強いため、周囲から信頼され、納得させることができます。
ただし、同じようなトラブルに対しても、相手の意見や状況に応じて柔軟に対応することが大切です。
マニュアル通りの対応だけでは、必ずしも望ましい結果を得られない場合があるため、臨機応変な対応力が求められます。
収益アップに繋がる
責任を持って仕事をこなすことで収益が向上する。
どういうことかと言うと、例えば、ある社員が責任を持って仕事をこなしているとします。
彼は常に業務のスケジュールや計画を遵守し、タスクを適切に遂行しています。
問題が発生した場合にはすぐに対応し、最善の解決策を見つけます。
また、上司からの指示に従い、顧客ニーズに応えるために努力します。
このような責任を持った仕事ぶりは顧客満足度を向上させ、収益の増加などの結果を生む可能性が高いのです。
リーダーシップの育成
ドラッカーによれば、リーダーシップは「仕事」であると考えられています。
リーダーシップは人々が生まれながらに持っている能力ではありません。
目標の達成や優先順位の決定など、組織管理に関連するタスクを遂行することで得られます。
この能力は、役職や立場によって決まるわけではなく、組織全体の結果に責任を持って取り組むことで得られる力。
つまり、責任を持った働きぶりがリーダー育成に直結していくのです。
将来への投資
主体的に自分の仕事に取り組むことで、能力や技術が磨かれます。
また、上司や先輩から取り組んだことが適切に評価されれば、その分満足感、自信を得ることができ、報酬やポジションを与えられるかもしれません。
自分の仕事に対する責任を持つことは、自分自身の成長だけでなく、将来的なキャリアアップに向けた重要な投資です。
責任を重く感じなくさせるコツ
仕事の責任を重く感じさせないためには、そもそも考え方を変えると、大きく改善されます。
「嫌だ」「できない」という否定的な感情を無くし、前向きに取り組める状況を作り出せればいいのです。
そのためにはいくつかポイントがあります。
ここでは責任を重く感じさせないコツを5つお伝えしていきますね。
責任を重く感じなくさせるコツ
- 責任を自ら重くしない
- できることから始める
- 1人で考え込まない
- 気負いして過労しない
- 失敗してもプラスになると考える
責任を自ら重くしない
コツその1、責任を自ら重くしない。
責任を重く感じるのは、周りから言われるか、自分の思い込み、このどちらかです。
「大事な仕事だから頑張って」と言われると、プレッシャーを感じ、仕事が一回りも二回りも大きくなります。
だから何を言われようとも、自分がブレないようコントロールして、ただ全うするだけ。
そもそも無責任な仕事なんてなくて、どんな仕事であれ、問題が起きれば担当者が責任を取るのですから、重いという感覚は要りません。
できることから始める
コツその2、できることから始める。
責任の重い仕事とは、少なくとも今よりワンランク上の仕事です。
できない仕事よりも、できる仕事の方が多い訳ですから、難しく考える必要はありません。
それに、自分の特徴を活かせば、自分なりのやり方がすぐに見つかります。
例えば私は、元々営業職ではなかったのですが、データに基づいた提案が得意だったので、それをそのまま営業に活かす、という方法を取りました。
恐らく、コミュニケーションスキルを身につけるとか、市場を読み解く力が必要だと、ほとんどの人は考えると思います。
もちろん必要なことですが、もしも苦手な分野であれば、かなり遠回りであり、うまくいかない可能性が高くなります。
だからまずは、「できることから始める」、これにつきます。
1人で考え込まない
コツその3、1人で考え込まない。
当たり前ですが、難しい仕事に取り組むわけですから、1人で何とかしようとするのは、大きな間違いです。
その筋に詳しい人、仲の良い先輩や同僚、なんなら社長に聞くなどして、しっかり助言を受けるべきです。
というのも、若い頃の私はとにかく臆病で、人に聞く、助けを求めるというのができず、ただただ孤独に暴走していたので、1人で、というのは絶対にお勧めしません。
何でもその道にはプロというのが存在します。
それは割と身近にいて、
- よく見なければ気付かない
- 深く付き合わないと知れない
といった場合があります。
「この業務苦手だなぁ…」
こんな時はまず、身近な人から手当たり次第に聞いてみましょう。
気負いして過労しない
コツその4、気負いして過労しない。
難題にぶつかり、なかなか解決できずに苦戦を強いられた時、「絶対やってやる」なんて気負いすると、無茶苦茶働くことになります。
その末路はご想像通り、
- 過労による体調不良
- モチベーションの低下
- 鬱、退職など社会離脱
とにかく悪いことしかありません。
先に述べた通り、責任の重さを大きくしているのは自分自身です。
だからあまり気負いせず、いつもの自分らしさを崩さない、ある意味マイペースでいることが大事なのです。
失敗してもプラスになると考える
コツその5、失敗してもプラスになると考える。
きっと多くの人は、「失敗するのが怖い」が前提にあって、責任の重い仕事をしたくないのだと思います。
失敗はもちろんしたくありません。でもそれは1つの経験として、後に「あれがあって良かった」と思えたりします。
それに、「あーあ」って落ち込むのは意外とその時だけ。
「あの時はうまくいった。」
「刺激的で楽しかった。」
「やってみて良かった。」
といったポジティブな記憶は残り、失敗は人の記憶に残らないものなのです。
だから、失敗って悪いことじゃない。笑いになることはあっても、決して悪いことじゃないんです。
責任に捉われずに、ひたすらこなすことです
繰り返しになりますが、「仕事の責任が重い」というのは、人からの期待と、自分の思い込みが大きくさせます。
難しい仕事、未経験の業務は、責任が重いのではなくて、ただ不安や怖さがあるだけです。
責任を重く感じさせないコツを掴み、仕事を楽しみ、自分の成長を感じてみてください。
最後に、責任を重く感じさせないコツをおさらいしておきましょう。
責任を重く感じなくさせるコツ
- 責任を自ら重くしない
- できることから始める
- 1人で考え込まない
- 気負いして過労しない
- 失敗してもプラスになると考える
こちらの記事もオススメ