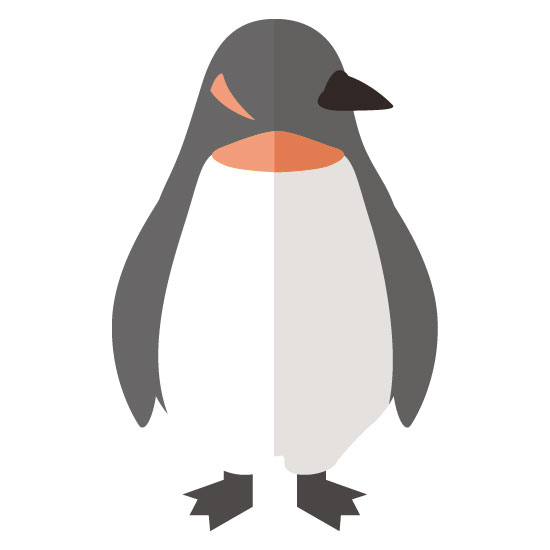この記事でわかること
- 遊ぶように働くことの特徴
- 遊ぶように働くために必要なこと
2019年にプロノイアグループ株式会社のピョートル・フェリクス・グジバチ氏が執筆した本「PLAYWORK」という書籍が話題となっています
タイトルが示す意味は、「遊ぶように働く」ということです
この考え方が、新しいワークスタイルとして注目されています
では一体、「遊ぶように働く」とは、どのような働き方なのでしょうか?
ポイント
たくさん働けば良いというスタンスは今後通用しなくなりますよ!
本記事のリンクには広告がふくまれています。
目次
遊ぶように働くことの特徴

皆さんの中にも、「遊ぶように働く」という言葉を初めて聞く人もいるでしょう
多くの人が企業で働いて、休暇やアフターファイブを自分の自由な時間・遊びに当てている方が大半だと思います
"働くこと=ON、遊び=OFF"という考え方が従来は常識でした
では、新しいワークスタイル「遊ぶように働く」とは、一体どういった働き方なのかを見ていきたいと思います
遊ぶように働くこととは?
- 仕事と遊びの境界線がなくなる
- 業務の自動化により単純作業がなくなる
- 創造性のある仕事が中心となる
- 個人事業主的な視点で仕事をする
- 組織に縛られず働く
- 様々な働き方ができる
- 労働時間の概念が変わる
仕事と遊びの境界線がなくなる
1つ目は、仕事と遊びの境界線がなくなることです
これまで仕事と遊びは、まったく別のものというのが常識でした
しかし「遊ぶように働く」とは、その境界線をなくしてしまおうというものです
“ワークライフインテグレーション”といったワークライフバランスより効果的な働き方も、海外では提唱されています
例えば、
「夕方からオフィスに友人を招いてデリバリーで食事を楽しみ、友人が帰った後、再び仕事に戻る」
「日曜日に買い物に出かけたついでに、1時間だけオフィスで仕事をし、また買い物を続ける」
こういった、従来のようにオンとオフをはっきり切り離さなず、どこからがオフで、どこからがオンなのかはっきりさせない自由な働き方が、今後増えるだろうと予想がされています
業務の自動化により単純作業がなくなる
2つ目は、業務の自動化により単純作業がなくなることです
近年、AIの研究がさかんにされるようになり、その発展はは驚異的で目を見張るものがあります
完全にAIが管理するオートメーション設備の製造ラインや、無人で運営されるコンビニなど、実際にAIが人間に変わって労働している事例もあります
オフィスワークにおいても、ストックデータから納品書や報告書、会議の資料を作成できるソフトが開発され、実用化の段階まできています
今まで時間を裂いてきた資料などの書類作りは、今後AIが代わりに作る時代がそこまで来ていて、私たちが単純労働から解放されていく未来も近づいているのです
創造性のある仕事が中心となる
3つ目は、創造性のある仕事が中心となることです
AIやロボットが驚くべきスピードで進化し、労働の概念が変化しているのは前項でも述べました
従来、我々の手を煩わせていた作業や書類中心のシステムから解き放たれた社会には、今までとは違った需要が発生するでしょう
今までにはなかった業務、全く新しい取引先からの要求が、今後、多く発生することになります
それらの新しい市場の需要に対して、新しいサービスを提供していくことが仕事の中心としてシフトしていくことでしょう
これからの仕事は、新しい何かを創造していくことが中心となっていきます
個人事業主的な視点で仕事をする
4つ目は、個人事業主的な視点で仕事をすることです
個人事業主は企業の従業員とは違い、出社時間などがなく自由で、時間に融通が利きますし、社則などに拘束されることもありません
逆を言えば定休日など決まった休みがありませんし、自分のマネジメントは自分でやります
平日でも仕事の都合が付けば自由に休めますし、休みの日でも、仕事をすることも自由にできます
いわば「遊ぶように働く」ことは、こういった時間や立場の自由を持った視点で仕事することと言えるでしょう
メモ
あの健康器具メーカー"タニタ"では、2017年より社員の個人事業主化を実施していますよ!
組織に縛られず働く
5つ目は、組織に縛られず働くことです
企業で働くとは、組織に属し、その組織の決めたルールや給与水準に則って働くことです
多くの人とすり合わせを行い、考え方の違う人間ともうまくやっていかなければいけません
こういった組織のデメリットから離れて自由に働くことが、「遊ぶように働く」ことを意味しています
様々な働き方ができる
6つ目は、様々な働き方ができることです
これといった仕事の概念や枠ににとらわれて働かなくても、自由に働くことができます
ライターをしながら、デリバリーの配達をして、帰宅後は動画クリエーターの作業をするなんてことも可能になります
自分の得意なことをサービスとして提供し、それを必要とする人がお金を支払うのを仲介してくれるサイトも登場しています
労働時間の概念が変わる
7つ目は、労働時間の概念が変わることです
従来の会社勤めのように朝に定時出社をしなくても、作業が滞りなく遂行できさえすれば、自分の好きなタイミングで働くことができます
人という生き物は、基本的に日中に活動して、夜に睡眠をとる生き物ですが、そのタイミングというのは一人一人の体内時計によって変わるといいます
これを"クロノタイプ"といい、いわゆる「朝方」「夜型」と呼ばれるものです
朝が強い朝方の人は日中に仕事をして、夜に活動する夜型の人は夕方から仕事をするというように、自分が活発な時間に仕事ができるのです
遊ぶように働くこととは?
- 仕事と遊びの境界線がなくなる
- 業務の自動化により単純作業がなくなる
- 創造性のある仕事が中心となる
- 個人事業主的な視点で仕事をする
- 組織に縛られず働く
- 様々な働き方ができる
- 労働時間の概念が変わる
「遊ぶように働く」という考え方には様々なものがあるようです
自分で時間やスケジュールを管理して、自分の興味のある仕事をして自分に合った働き方をしていくのが、その基本となるようです
このようなことを踏まえて、次に遊ぶように働くために必要なことを見ていきましょう
遊ぶように働くために必要なこと

従来の仕事の概念にとらわれず、遊ぶように働くにはどういったことが不可欠なのでしょうか?
いくつかあげてみますので、皆さんのヒントになるかもしれませんよ
遊ぶように働くために必要なこと
- 自分のやりたいことを知る
- 固定観念から解き放たれる
- 自分が楽しいと思える仕事を増やす
- 自分にしかできない仕事をする
- 新しい価値を創造し提供する
自分のやりたいことを知る
1つ目は、自分のやりたいことを知ることです
「あなたが本当にしたいことは何ですか?」という質問に、即答できる人はあまりいないかもしれません
日々、忙しく過ごしていると、自分の本当の願望に気づけないことも多いですね
働き方を変えたいなら、自分の今を見つめ直して、本当に自分のやりたい仕事に気づく必要があります
自分のやりたいことがわかれば、新しい自分の生き方への手がかりが見つかっていくでしょう
固定観念から解き放たれること
2つ目は、固定観念から解き放たれることです
今までは「仕事はお金を得るためのやむを得ない手段だ」「仕事は楽しくないものだ」といった働くことへの固定観念がありました
長年、それを世間の常識として、人は受け入れてきました
しかし、我々が生きている世界は広大で、全く違う考え方の人間も存在しています
自分が気づきもしなかった考え方に出会い、自分の常識を疑い、当たり前だった固定観念を打ち破っていくことが、非常に重要になります
自分が楽しいと思える仕事を増やす
3つ目は、自分が楽しいと思える仕事を増やすことです
まず、仕事において、自分は何が楽しくて、何が楽しくないのかを把握してみましょう
"楽しい仕事=得意なこと・興味があること"だと気づくはずなので、楽しいと思える仕事がわかったら、それを増やしていきましょう
楽しいと思える仕事を専門にフリーランスで仕事をしていったり、組織内では自分の得意な仕事を積極的にやって、苦手な仕事はそれが得意な人に任せるようにしていけば、夢中になって仕事をしていけるかもしれません
自分にしかできない仕事をする
4つ目は、自分にしかできない仕事をすることです
「あなたにだから、この仕事をお願いしたい」とクライアントに言われると嬉しいものです
認められた充足感は、次の仕事へのモチベーションを生み出します
同じ仕事でも、あなたが自分で考え、工夫して、あなたの感性を使って仕上げたものはあなたにしかできない仕事だと言えます
上には上がいる、なんて思ってしまいがちですが、そんな考えは捨ててしまいましょう
新しい価値を創造し提供する
5つ目は、新しい価値を創造し提供することです
これからはAIが発展し、様々な仕事をする時代になっていくことでしょう
いわば、今までのニーズに変わって、全く新しいニーズが発生してきます
AIにはできない「クリエイティブな感覚」を世の中へ価値として生み出していくことが、人間の役割になってきます
これに伴い、市場や世間のニーズに耳を傾け、新しい価値あるサービスやシステムを提供していくことが大切になってきます
遊ぶように働くために必要なこと
- 自分のやりたいことを知る
- 固定観念から解き放たれる
- 自分が楽しいと思える仕事を増やす
- 自分にしかできない仕事をする
- 新しい価値を創造し提供する
「遊ぶように働く」ために必要なことを見てきました
この考え方は、今から人が人生を生きていくために不可欠な考え方だと思います
これからさらに、加速度的に変化していく時代に希望を見失わないためにも、「遊ぶように得意なことをする」「好きなことを仕事にしていく」ことは、私たち人間の必要不可欠な課題となっていくに違いありません