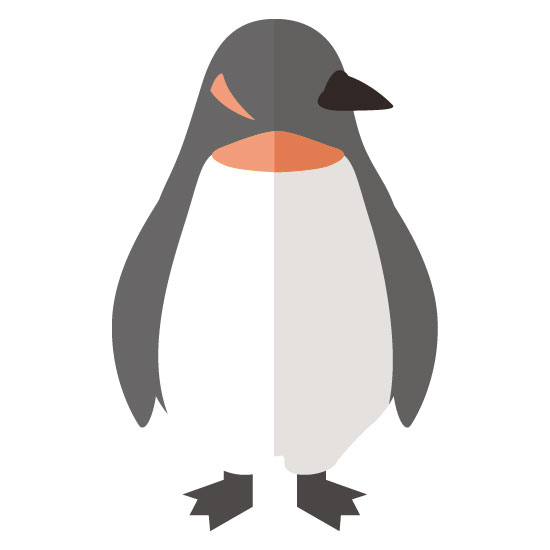この記事のお悩み
- 長々と文章を書いてしまう…
- どこで話を終わらせていいか分からない…
- 時間をかけずに文章を作りたい!
このように、私も文章を書くのに時間がかかり悩まされたことがあります。
本記事で解説する、「読まれる文章をかけない人が、読み手に伝わる文章を書く方法」を理解すると、簡単にスラスラと読まれる文章が書けるようになります。
文章を書く時間もめちゃくちゃ短縮されるようになりますよ。
目次
本記事のリンクには広告がふくまれています。
スラスラ読める文章を作るポイント
読まれる文章は読み手にストレスを感じさせません。
スラスラ読める文章を書くには、次の3つのポイントが重要です。
スラスラ読まれる文章を作るポイント
- 短文で書く
- 丁寧さは要らない
- 書いたら必ず見直す
ではそれぞれ解説していきます。
短文で書く
伝えたいことが多すぎると、文章はどんどん長くなります。
長文は疲れるし、途中で飽きたり読むのが嫌になってしまいます。
そのため、まずは文章を短くしましょう。
1つの文で「丁度いい」文字数は、40文字〜60文字。大体2,3行程度に収まる感じです。
例文を挙げると次のようになります。
元文
昨日の昼間、私は空いた時間で本屋に立ち寄り、小一時間立ち読みをしていたのですが、たまたま面白い本を見つけて読んでいたら、気付けば14時を回っていて、うっかり待ち合わせの時間に遅れてしまいました。
短文に添削
昨日の昼間、時間が空いていたので本屋に立ち寄りました。
そこで見つけた本が面白くて夢中になっていたら、気付けば既に14時。
没頭しすぎて、うっかり待ち合わせの時間に遅れてしまいました。
このように短文にすると、淡々とリズム良く読めるようになります。
丁寧さは要らない
スラスラ読める文章には、まわりくどい表現がほとんどありません。
なぜかと言うと、まわりくどい表現はストレスを与え敬遠されてしまうからです。
例えばビジネスにおいて使われがちな敬語、謙譲語には、次のような表現があります。
「〜してもよろしいでしょうか?」
「〜していただけますでしょうか?」
「〜いたしますがいかがなさいますか?」
どうですか?特に最後は見ているだけでイライラしませんか?
丁寧に伝えたい気持ちは分かります。
ですが最も大事なのは、読み手にスッと入るかどうかです。
文章はシンプルに伝えること。パンパンに詰まった敬語だらけの文章なんて読みたくありません。
書いたら必ず見直す
作家さんや出版社の方は、書いた文章の「校正」と「校閲」を行います。
| 校正 | 誤字脱字など文章の表記に誤りがないか? |
| 校閲 | 文章内の情報が正しいものか? |
プロのレベルまでは無理だとしても、「誤字脱字」「情報元」などは、見て調べれば素人でも直せます。
過去に私は台本作りを外注した際、プロの作家さんに校正と校閲をお願いしたことがあります。
その時に「何をチェックしているか?」と要点を伺ったら、「台本を書いている人が素人なので、誤字脱字や言い回しなどを重視している」と言っていました。
一度書いた文章をひと通り見直すと、漢字の誤り、内容の重複などが見つかります。
短い文章が伝える!スラスラ読める文章の組み立て方
読まれる文章を作るには、文章を組み立てる技術が必要です。
と言っても、論文を書くのとは違って、特別なスキルが必要な訳でもありません。
私はブログを通して文章を書くスキルを身につけました。
この記事でようやく「形になったかな」程度ですが、これからお伝えすることを取り入れると、きっとスラスラ書けるようになります。
完全に素人の私でさえ、それなりにアクセスを得られるブログができているので安心してください。
では、スラスラ読める文章の組み立て方を解説していきますね!
見出し(全角15文字)
- 文末(語尾)を統一する
- 1文で読点は2つまでに抑える
- 書いた文章を簡潔にする
- 主語と述語を近づける
- 経験談や実例を添える
- 箇条書きにする
- 結論から述べる
- 読み手のことを考える
- 強調したい時は文字を目立たせる
- あえて漢字を省く
文末(語尾)を統一する
文章の文末(語尾)を統一するだけで、読んでいて違和感がなくなります。
語尾に使われる言葉には主に、
- 〜です
- 〜ます
- 〜だ
- 〜である
があり、1と2をセット、3と4をセットにするとスッキリまとまります。
例えば夏目漱石の「我輩は猫である」は3と4の組み合わせです。
原文
吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。
これを1〜4の組み合わせにすると、
吾輩(私)は猫だ。名前はまだありません。どこで生れたか頓と見当がつかない。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶しています。
このように、語尾がバラバラだと読んでいて気持ち悪くなります。
1文で読点は3つまでに抑える
短文で書くことを意識すると、1つの文章で読点を使いすぎないこと。
1つの文で「丁度いい文字数」は、大体2,3行程度に収まる程度なので、読点は多くても「3つまで」がベストです。
読点を打つポイントは以下の通り。
| 位置 | 例文 |
| 主語の後 | 今日の朝ごはんは、大好きなパンだ。 |
| 接続詞の後 | しかし、いつものパンじゃない。 |
| 文の境目 | 我が家では食パンが主流なのに、今日は珍しくフランスパンが出てきた。 |
| 名詞などの並列 | テーブルの上には、ジャム、バター、オリーブオイルが並んでいる。 |
| ひらがな、カタカナ、漢字の続き | 私がバターを塗ろうとしたら、いつの間にか弟がバターを手に取っていた。 |
また、文を書いていて「あ、ここで区切った方がいいな」と感じるところに読点を置くと、割と自然な形になりますよ。
書いた文章を簡潔にする
長々と書いてしまって「なんか読みづらい」と感じたら、要らないワードを削除し、文章をギュッと縮めます。
- 不要な語句
- 曖昧な表現
- まわりくどい言い方
- 同じ意味の反復
などを削除し簡潔にするのです。
また反対に、あらかじめ文章を短文で作るよう心がければ、簡潔にする手間が省けます。
私がブログを書く時は、基本は短い文章にし、2文を1文に繋いだりしています。
とにかく短文で書き、くっつけるだけの作業です。
主語と述語を近づける
短文で書くコツは、主語と述語を近づけることです。
主語:「何が」
述語:「どうする・どんな様子・なんだ」
文の土台はこの2つで、その間に修飾語や接続語を肉付けしたものが文章です。
読みづらい文章ほど、主語と述語の間に余計な装飾があります。
例文
- 「
街を歩いていると大きな荷物を持った人が後ろからバタバタ走ってきた。」 - 「今朝、小雨が降っていたので、
雨に濡れないよう(私は)傘を持って出かけた。」
このように、無くても良い文を削除すると読みやすくなります。
体験談や実例を添える
小難しいことを述べる時ほど、自身の体験や実例を添えると読みやすくなります。
ここでも文法について触れながら、所々に私の体験や例文を加えていますよね?
その方が伝わりやすく、読んでいてストレスを感じないからです。
また、体験談や実例を添えると「説得力」も増します。
例えば、
Aさん:「新宿にある〇〇というカフェは有名だから美味しいと思う。」
Bさん:「新宿にある〇〇ってカフェに行ったら、マンゴースムージーが美味しくて、調べたら評価も良かった!」
どちらの方が説得力があるか明確ですよね。
ただ淡々と書くよりも、体験談や実例を文章に取り入れた方が、断然読みやすくなります。
箇条書きにする
伝えたい情報を簡潔に見せるには、「箇条書き」が便利です。
1文の中で情報を詰めすぎると、文字が渋滞し読みにくくなります。
箇条書きは以下のように、同じ要素をまとめる時に使います。
- 数(円、人、%など)
- 名前(人名、地名、種類など)
- 見出し
- 問題点
また箇条書きは、優先順位をつけて書く方法もあります。
実際に身近なものでは、「加工食品」「飲料水」「洗濯表記」など、成分の割合が高いものから順に記述されています。
番号を振ると「時系列」にもなるので、箇条書きはうまく使いこなしましょう。
結論から述べる
時間をかけずに文章を書きたい場合、最初に結論から述べます。
読み手は「これを読んで何が得られるか?」が知りたいので、冒頭に結論があると手っ取り早いのです。
結論から伝える文章を書く際、「PREP法」がよく使われます。
| PREP法の構成 | |
| P=Point | 結論、主張 |
| R=Reason | 理由 |
| E=Example | 事例、具体例 |
| P=Point | 結論、主張 |
PREP法の例文
P:「早起きは三文の徳です。」
R:「なぜなら時間を独り占めできるからです。」
E:「外は静かだし子供も寝ているので、ゆっくりと時間が流れているのを感じます。」
P:「子供のいる家庭は尚更、早起きは三文の徳でしかありませんよ。」
このようにPREP法を活用すると、伝えたいことが論理的に整理されます。
またこれにより得られる効果は以下の3つです。
- 読み手にストレスを与えない
- 文章が整理される
- 書くスピードが上がる
PREP法を使い結論から述べると、文章は伝わりやすくなります。
読み手のことを考える
当たり前ですが、書いた文を読んでほしいのであれば、読者の「心理」を読まなければいけません。
それを無視すると、ただの独りよがりになってしまいます。
コミュニケーションにおいても、相手の気持ちを汲むのは鉄則です。
一方的に話したり、何でも思ったことを口にすると嫌がられ、人間関係がこじれます。
文章の場合、書き手と読み手はその場にいません。
書いた先に読み手がいることを想像しながら、以下の点に注意して書きましょう。
- 上から目線で話さない
- 内容に沿ったことを書く
- 読み手の悩みをよく考える
- 自分の想いを伝える
強調したい時は文字を目立たせる
文章の中で強調したいところがある場合、その部分を目立たせます。
書籍、ブログ、ネットニュースでも、主張したい部分は次のように変えたり書き加えています。
- 見出しをつける
- サイズを大きくする
- 文字を太くする
- アンダーラインをつける
これにより、読者に対して「重要なポイント」「役立つ情報」などが視覚的に伝わり読みやすくなります。
見出し以外の部分は使い過ぎずに、適度に入れた方がストレスを与えません。
あえて漢字を省く
漢字を羅列して書くと、読むのが疲れるので漢字を省きます。
ただでさえ日本人は活字離れしているのですから、読み手に「つらい」と思われないようにします。
実際に私が仕事のメールにあった、漢字の羅列による読みにくい文を挙げます。
「至急改善対策の御提示をお願い致します。」
「御確認何卒宜しくお願い申し上げます。」
見るだけで「うっ…」となりませんか?
前述した「丁寧さは要らない」と同様、漢字を使いすぎるのも不快を与えるので、ひらがな・カタカナを混ぜて柔らかい文章にしましょう。
スラスラ読める文章を書くなら短くシンプルにすること!
繰り返しになりますが、スラスラ読める文章を書くためには次の3つのポイントを押さえることです。
スラスラ読まれる文章を作るポイント
- 短文で書く
- 丁寧さは要らない
- 書いたら必ず見直す
また次の「文章を組み立てるスキル」を身につけること。
スラスラ読める文章の組み立て方
- 文末(語尾)を統一する
- 1文で読点は2つまでに抑える
- 書いた文章を簡潔にする
- 主語と述語を近づける
- 経験談や実例を添える
- 箇条書きにする
- 結論から述べる
- 読み手のことを考える
- 強調したい時は文字を目立たせる
- あえて漢字を省く
作家でも小説家でもない素人の私でさえ、このように文章が書けるようになっています。
あなたも正しい書き方を身につければ、読まれる文章を作ることができますよ。